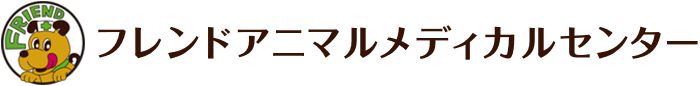行動診療科とは
行動診療科は、犬や猫の問題行動や心の不調を専門的に診る診療科です。「困った行動」は、しつけや性格だけの問題に見えることもありますが、不安・恐怖・ストレス・疾患などが背景にあることも少なくありません。
よく見られるお悩み例
- 過剰な吠え、噛みつき
- トイレの失敗
- 分離不安(留守番中の破壊行動や吠え)
- 雷や花火への極度の怯え
当科では、行動学的評価・環境調整・行動療法・薬物療法を組み合わせ、 飼い主様とペットがより良い関係を築けるよう支援します。
代表的な問題行動
| 行動タイプ | 主な例 |
|---|---|
| 攻撃行動 | 噛みつき・威嚇(人や他の動物へ) |
| 過剰な吠え | 要求吠え・警戒吠え・留守番中の吠え |
| 不適切な排泄 | トイレ外での排泄・スプレー行動 |
| 分離不安 | 飼い主がいないとパニック・破壊行動 |
| 恐怖症 | 雷・花火・車・人混みなどへの過剰な反応 |
| 常同行動 | 尾追い・体を舐め続ける・毛むしりなど |
| 認知機能不全症候群(認知症) | 徘徊・昼夜逆転・鳴き声・トイレの失敗など |
検査・評価方法
行動診療科の診察では、問診と観察が診断の鍵となります。
1問診・ヒアリング
- 問題行動が起こる状況・頻度・きっかけ
- 家庭環境や生活習慣
- 動画記録の提出も推奨
2身体検査・医学的検査
- 行動の裏に病気(痛み・尿路疾患・脳疾患など)が隠れている可能性を確認
- 必要があれば血液検査・画像診断なども併用
3行動学的分析と診断
- 不安・恐怖・欲求不満など、動機に応じた行動診断に基づく治療プランのご提案
- 継続的な診察と評価で、都度治療プランを調整
治療方法
治療は主に以下の3つの柱を組み合わせて行います。
1行動療法(トレーニング)
- 応用行動分析に基づく、動物福祉に配慮したトレーニング法のご提案
- 飼い主様とペットの生活におけるルール作りのお手伝い
- お手入れなどの苦手を克服するための、陽性強化法を用いたトレーニング・レッスン
- 不安・恐怖症に対してのポジティブトレーニング
2環境調整
- 視覚・聴覚刺激の遮断(遮光カーテン、防音対策など)
- 清潔で安心できるトイレ環境
- 落ち着けるスペース(クレート、サークル)の設置
- 運動量の確保・知育玩具での刺激提供
3薬物療法(必要に応じて)
抗不安薬・抗うつ薬
例:クロミプラミン、フルオキセチン、トラゾドン、ベンゾジアゼピン系など
抗不安効果のあるサプリメントの使用
認知症対策
ドネペジル(アセチルコリンエステラーゼ阻害剤)、抗酸化サプリメント、漢方療法など
※薬はあくまで補助的手段であり、行動療法と併用することで効果が高まります。
手術方法について
行動診療科において、直接的な外科手術は基本的に行いません。ただし、以下のようなケースでは関連があります。
去勢・避妊手術
撃性やマーキング行動、発情による落ち着きのなさの改善に効果があることも
自傷行為による外傷
深い傷の縫合処置などが必要な場合あり
安全対策としての爪処置
自傷や過剰な興奮による事故防止のために一時的に実施すること
撃行動が深刻な場合の犬歯を短く切る処置
とはいえ、行動修正・環境調整が主軸であり、手術はごく限られた補助手段に過ぎません。
その他特筆すべきこと
行動の問題は「しつけの失敗」ではありません。ペットの行動には必ず理由があり、科学的アプローチで改善可能です。
飼い主様にお願いしたいこと
- 罰や力での制止はNG
根本解決にはならず、問題を悪化させたり、信頼関係を壊すリスクがあります - 継続と根気が鍵
スモールステップで成功体験を積み重ねることで、飼い主様やペットに無理のないトレーニングをご提案いたします - 認知症は「歳のせい」で片付けない
環境やサプリで改善できるケースも多くあります
行動の悩みはデリケートな問題で、相談しにくいと感じることもあると思います。
しかし、当科ではどんな小さな悩みにも真摯に耳を傾け、一緒に改善策を探すパートナーとしてお手伝いします。
ペットとの毎日がもっと笑顔に満ちたものになるよう、ぜひお気軽にご相談ください。